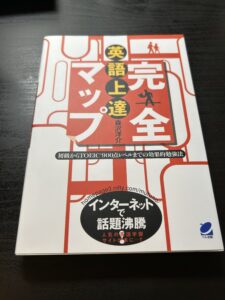明日は税理士試験
税理士試験ですね。私は国税の職場にいたときに簿記論と財務諸表論を取得しました。
国税の職場では大卒相当で入った職員が3年もしくは2年の実務経験を積んだのち同期が全員で専科研修という研修を受けます。
その研修でいい成績をとると、職場人生が楽しくなるよと言われたので、良い成績を取るために事前に簿記の勉強をかなりがんばっていました。
研修の1年ほど前から簿記の勉強を継続して、結果的には研修中に日商簿記検定1級にも合格でき、研修でもよい成績(優等賞=いわゆる金時計というやつで研修参加者の上位5%の成績)をいただきました。
研修が終わったのが2月の末で、その後は税務署に戻るわけですが、そのまま簿記の勉強は毎日続けていました。
やることは毎日朝早く通勤して、署の最寄り駅のスタバで40分から50分ぐらいかけて簿記の総合問題を1問解いてから出社するということだけをやっていました。
それでその年の税理士試験で簿記論も財務諸表論も合格できました。ある意味運がよかったと思っています。
国税職員の試験免除制度
国税の職場では23年勤務すると税理士となる資格をいただくことができます。正確には先に挙げた専科研修(高卒相当の場合は本科研修)等で会計学に相当する授業できちんとした成績をとることが要件です。
そもそも23年勤めた結果をもって免除されるのに一時、しかも通常は若手の時に受講した研修の成績が必要なのは謎ですが・・・
ただ税理士試験と違って落とす試験ではなく、通常はほとんどの人が受かる試験です。しかも一度落としても再試もあります。それでもここ数年は落とす人が昔では考えられないぐらい続出していて、大変みたいですが。
なお、これらの研修を落としても会計の通信研修に参加してその通信研修で合格すればいいという二重の救済措置もあります。
それ以外に10年勤務すると税理士試験の税法科目が免除される制度もあり、その場合は簿記論と財務諸表論を自分で合格すれば23年の勤務を待たずに税理士となる資格を得ることができます。
税理士の世界では批判もある制度だと思いますが、もらえる側からするとありがたい制度です。
ただ、資格を取得しても辞めてまで実際に税理士となる人は多くないですし、定年退職しても再任用といって国税の職場での働き続けることを選んで、税理士になる方は多くはないです。
国税職員も受けている
明日からの税理士試験は国税の職員が運営側でも動員されています。しかしながら有給や夏休みをとって受験者側で参加する税務職員も結構いるはずです。
その時期にはあの人も税理士試験を受けたらしい、試験会場で何々さんを見かけたといった話を聞くことがありました。
自分もそうでしたが、努力すること、積み重ねることは大変なことです。
税理士試験、受験する方はがんばってくださいね!